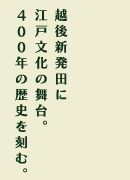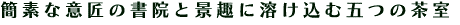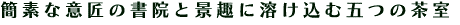
     

このあたり一帯が清水谷(しみずだに)の地名であったため、清水谷御殿、清水谷御座敷、または清水谷とよばれていた「清水園」。 新発田藩が、曹洞宗高徳寺を五十公野上新保(新発田市)に移し、跡地に下屋敷をつくるための整地をしたのは寛文元年(1661)。棟上げが行われたのは同年6年4月。記録による「清水谷御座敷普請」の完了は元禄6年(1693)11月2日。棟上げから完成まで、じつに27年もの歳月を費やしたことになります。
明暦3年(1657)の江戸大火による上屋敷類焼、寛文8年(1668)には新発田城全焼、追い打ちをかけるように翌9年の新発田城の石垣が崩壊する大地震。これらの再建復旧工事のため、工事が中断されたためと考えられています。
園内に入り最初にくぐる萱葺の大門は、藩家老や藩知政庁に構えていたもの。そのさきの中門は、江戸初期の茶匠、千宗旦の高弟・藤村庸軒が京の黒谷、淀看の席の入口に建てた門を新発田に運んだものとされています。
大門と中門を結び、新発田川に平行して園の南端まで小砂利の道がのびています。かつては百間(180m)馬場とよばれ、ここで馬術や弓術の演練が行われました。
中門の手前、右手にある寄棟造平屋(80坪)の屋根は、古くは柿茸でしたが、のちに桟瓦葺、現在は鉄板葺となっています。 京間座敷(幅2間・奥行4間半)を中心に、奥には2畳敷の上段の間と1間の床、庭に面した南側は縁側で開放され、庭とあいまって心憎いばかりの景観の調和を見せます。 この座敷から鍵の手に北へ続く次の間(15畳)に、2間床を設けてあるのは江戸初期の慣例といわれます。床には春慶塗がほどこされ、床下に甕(かめ)を伏せたらしき跡があることから、この部屋は能舞台に用いられたと考えられています。
また、古い記録によれば、書院の腰高障子は、寛文8年の城内全焼の火災の際、搬出して焼失を免れた城中大書院腰高障子を、当時の藩主重雄は「古きを残さんと思し召して清水谷へ御用い給い」と残したものです。 きわめて簡素な意匠で、幕府に対する政治的配慮がされた、江戸初期の下屋敷の面影を偲ぶことができます。
■昭和29年11月20日、県有形文化財指定
■平成15年8月27日、旧新発田藩下屋敷(清水谷御殿)庭園および五十公野御茶屋庭園として国名勝指定
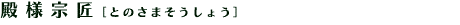
城下町新発田は茶の湯が盛んです。その主流を占めているのが、石州流怡渓派流祖を名のるなどの歴代藩主。 石州流の開祖は、徳川4代将軍家綱の茶道師範役でもあった片桐石見守貞昌(石州)ですが、この宗匠・石州の高弟怡渓宗悦(石州流怡渓派)に茶の湯を学んだのが重雄であり、5代重元も父重雄に茶事を習いました。 とりわけ10代直諒は、藩の江戸末期の茶匠阿部休巴に茶道を習い、奥義を極めるにいたるほどでした。休巴の師・藤重藤厳は、怡渓宗悦の流れを汲む3代伊佐幸琢の弟子であることから、直諒は石州流越後怡渓派を樹立、宗匠となりました。
殿様宗匠の誕生は、家臣をはじめ町人にも大きな影響を与え、以後、新発田には、藩茶道の伝統が受け継がれていきました。
「清水園」の池のまわりには、「桐庵」「夕佳亭」「翠濤庵」「同仁斎」「松月亭」それぞれ趣の異なる茶室が配されています。これは荒廃した庭園の修復工事と併せて、茶人田中泰阿弥が清水谷御殿絵巻物や古記録にもとづき、昭和20年代に築造したものです。
清水谷の古地名は、加治川の伏流水が推積層を通して、一帯に湧き出ていたからかもしれません。近年まで園内の井戸水は、酒造りに用いられていました。藩主などがここの名水で、茶の湯を楽しんだことは、おおいにうなづけることです。 |