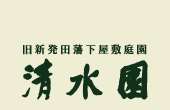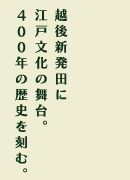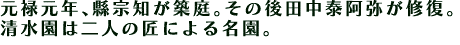
庭園は、4代藩主重雄の元禄年間に築造された。作庭したのは遠州流茶人・上柳■斎の門下で、幕府庭方の縣宗知(1656〜1721)である。新発田へは4度招かれたとされるが、記録では、元禄7年(1694)4月、幕府の御坊主縣宗知、新発田城へ登城に付き表門を開き、羽織袴の小頭や足軽が土下座して迎え、物頭が上下正装して接待した、と宗知に1度だけ触れている。幕府に対する藩の配慮ぶりが窺えるのである。 宗知と新発田藩のかかわりはこれが初めてではない。これより3年前、「元禄3年、八丁堀御座敷ハ御上屋敷前之御寝間御移シ、縣宗知好御露地■出来」と藩記録にあるからである。 一方、当時の藩主重雄は自ら石州流越後怡渓派流祖と称したほど茶の湯を通じて両者が結びつき、清水谷の築庭に宗知が招かれたものと思われる。
【新発田真景絵巻】 昭和20年代、清水谷御殿は清水園と名称を変え、茶席を含めた庭園は修復されることになる。庭師は銀閣寺の清泉の石組みの発掘復元をはじめ、各地の寺院や名園の修復を手がけた田中泰阿弥である。京都から運んだ石を使い、古記録に基いて修復した庭園は、茶席と池泉が一体となって景観に溶け込み、越後から東北にかけて他に比を見ない大名様式を伝える名園である。 |
 |
 |
 |
 |
| 池の南東部にはカメ島と呼ばれる小島がある。 黒い石をカメの頭に見たて、背の小島には、苔がおおい、2本の小松と、 春になるとツツジが緑の中に色を添える。 | 昭和50年の晩春、泰阿弥77歳の祝いの茶会を記念して清水園の築山のふもとの小道の端に、歌碑がたてられた。
くくくとなき ころころとなき かかとなく これさ蛙のよろこぶうたか 泰阿弥 と刻まれている。 |
同仁斎の近くにある燈籠は、鎌倉時代の作であり、小町燈籠と呼ばれている。また、笠塔姿を真似て仏をきざんだ織部灯籠は、桃山時代以後の作で、台座がなく、埋め込み式の珍しいものである。どちらも重文に値するといわれている。 | |